
計装機器について学習しているんだけど、伝送器や検出器とか同じような用語が多くてよく分からないや….
計装機器について学習していると様々な計装機器がつながって一つの制御をしていることに気づくと思います。
今回はそれらの計装機器である検出器、変換器、伝送器について役割含めて解説していきたいと思います。
検出器
検出器は温度や圧力、流量などを直接的に測定するのに用いられる機器です。計装記号でいうと「E」で表されます。
計装記号に関しては以下で解説しています。
例えば、測温抵抗体は抵抗素子の温度変化によって抵抗値が変わることを利用した計器です。一定の電流を流して、両端の電圧を測定することで温度を導き出すことができます。
また、電磁流量計はコイルに電流を流して計測管内に磁界を生成して、その中を流れる導電性液体の流速によって発生する起電力の大きさを検出することで流量を測定する計器です。
しかし、これらは測定する対象および方法によって取り出せる信号が異なっており、それだけでは計器として利用しにくいものが多いです。
そのため、これらは一般的に次に説明する変換器や伝送器と共に用いられます。
変換器
変換器は諸量の検出を行って生じた電気信号や機械変位に加工を施し、測定に便利な出力信号として取り出せるようにしたものです。計装記号でいうと「Y」で表されます。
ここで測定に便利なものとは4~20mAで表される電流信号や1~5Vなどで表される電圧信号があります。

一般に市販されている計器類は検出器と変換器は一体となっていて販売されているものも多いよ!
上に記載の通り基本的な流量計などは検出器と変換器は一体となっていることが多いです。
逆にオリフィスやpH計などは検出器としての役割しか持たず、別途変換器が必要になってくるイメージがあります。
伝送器
最後に伝送器ですが、これも変換器と同様に諸量の検出を行って生じた電気信号や機械変位に加工を施し、測定に便利な出力信号として取り出せるようにしたものです。計装記号では「T」で表されます。
一般的には4~20mAの電流信号として使用されることが多いでしょうか。
伝送器は特に圧力や差圧の検出に用いられることが多いと思います。

伝送器には電源が必要な変換器とは異なって、電源が必要ない2線式なのが特徴だね!
2線式と4線式の違いについては以下の記事で紹介しています。
まとめ
今回は検出器、変換器、伝送器について記載してみましたがまとめるとこのような感じでしょうか。
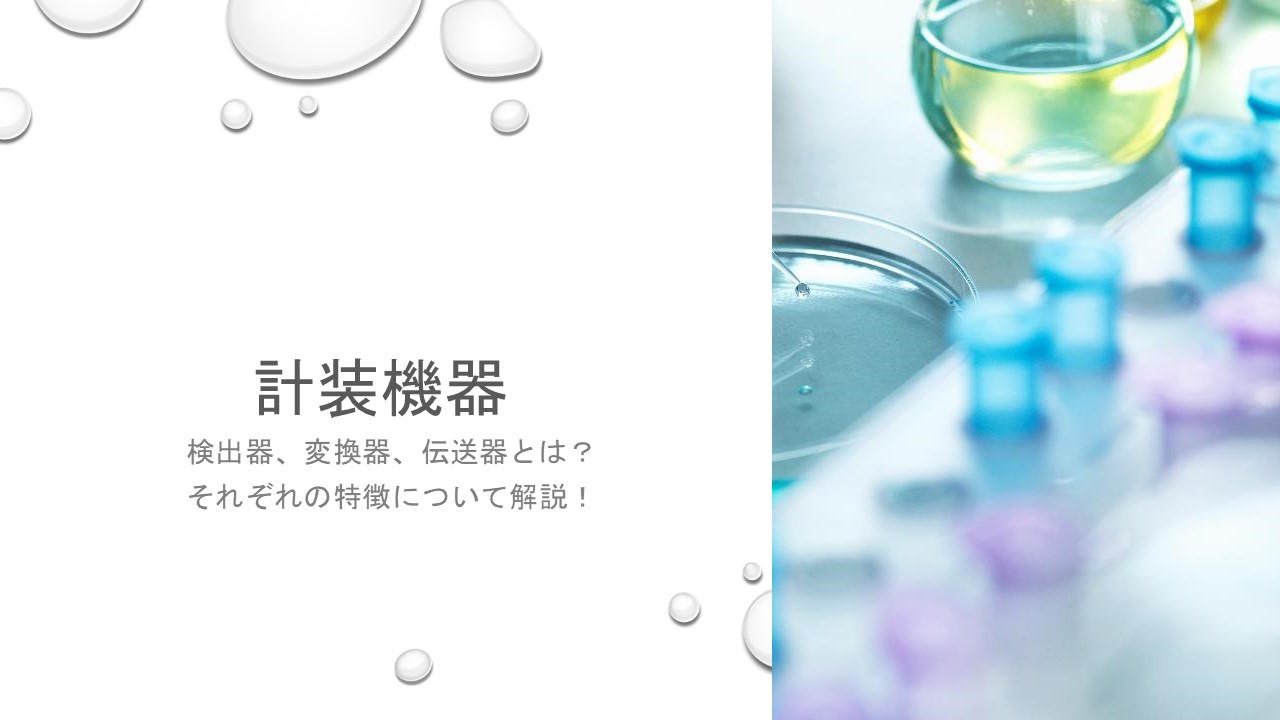




コメント